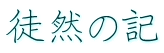 |
|
| タイトル | 記 事 |
| 2021年3月30日(火) 「子どもの主体を起こす読み優先の漢字教育」 実践の深化 |
まずは「漢字が読める」に焦点を当てた『漢字音読名人』は、取り組んだ全ての学級で顕著な成果を挙げた。 更に、読みをベースに『一日一漢字』『漢字書き名人』の教材を整備し、これら3教材をトータルに使って指導した学級では、漢字の習得率がほぼ全員9割を超え、読書量も飛躍的に増加した。詳しくは、開設している下記サイトをご覧いただきたい。 4月から始まる新しい1年。こ;れらの教材を使って、子どもたちの笑顔と学びの意欲いっぱいの教室が生まれることを、心から願っている。 |
| 2020年5月2日(土) 「子どもの主体を起こす 読み優先の漢字教育」 サイト開設 |
臨時休校中の子どもたちが家庭で楽しく漢字学習に取り組める、家庭学習支援サイトを新たに作りました。 読み優先の漢字教育を進めるため作成した教材のうち、漢字の成り立ちから、意味・読み・文例・筆順までを学べる「一日一漢字」パワーポイントデータを動画化したもの、カルタ遊びを楽しみながら漢字の音・訓読みが習得できるようにした「漢字音訓カルタ」を仮upしています。 休校中の自宅学習にしんどい思いをしている子どもたちも、「漢字の勉強っておもしろいなあ!」と思ってくれるのではないかと期待しています。一度、このサイトを見ていただけるとうれしいです。 |
| 2020年4月14日(火) 「読み優先の漢字教育」に取り組んで |
昨年一年間、「読み優先の漢字教育」の教材づくりに没頭して、hp更新どころではなかった。 今、ようやく新教材チェックの段階まできた。 新型コロナウイルスで全国ほとんどの学校が臨時休校の措置をとっているので、この間にチェックを済ませ、学校が再開したら活用してもらえるようにしたいと思っている。 これまでの取り組みで確信していることは、「これは、単なる漢字の効率的な指導ということにとどまらず、主体的対話的な学びを引き出し、子ども自身の生きる力を育む教育そのものだ」ということである。 滋賀の一市から始まったこの取組は徐々に県内に広がりつつある今後、更に実践の輪が広がることを願ってやまない。 |
| 2019年7月11日(木) ドル平のポイント指導 |
泳げない子も必ず泳げるようになる「ドル平」実践を広げたくて、今関わっているH小3年に紹介し、取り組んでもらっている。 「けっこういい感じにはなってきているのですが、息継ぎがうまく行かないのです。」 という担任の声を受けて、「もう一度、ポイントをおさらいする形でやってみてください。」と言って指導資料を作った。 私も一緒に指導してみた。「いち・にー・さーんパッ」はできているのだが、伏し浮きから続く息継ぎというところが形にならない。そこに焦点を当てた練習が決め手になる。1時間、この息継ぎ練習をやれば劇的に泳げる子が増えると期待する。 |
| 2018年12月28日(金) 漢字読み書き名人の試作 |
漢字の読み優先指導に取り組んで4年。漢字の読みに焦点を当てた漢字学習の有効性は十分に検証できた。 残る課題は「読めるようになった漢字は、書く練習も簡単になる。」ということの実証である。 その検証を進めるための教材として「漢字読み書き名人」を試作している。表ページはすでに作成している「漢字音訓カルタ」で読みの練習。完璧に読めるようになったら友達に聞いてもらう。合格できたら書きの練習。「何回で書けるようになるか?」と挑戦させる。漢字の読みも意味もあいまいなまま練習するのに比べて少ない回数で書けるようになるだろうと期待している。そして書く自信がついたら友達の前で書いて○をつけてもらう。 教師の手を介さず子ども同士で進めていく。その方がずっと子どもの主体的な活動になる。 東京書籍版教科書準拠の3学期分については作成できたので、upした。 ぜひ試していただきたい。 漢字読み書き名人 |
| 2018年11月23日(金) 漢字音読名人『ビーバーの大工事』編 |
漢字の読み優先指導をA小2年「ビーバーの大工事」の学習の一環で試してもらった。教材文から抜き出した短文を上学年の漢字もルビ付き表記にしたワークプリントを作りその単元の学習に入る前の音読練習として取り組んでもらった。学習後どれだけ読めるようになったか、漢字の読みチェックテストをしてもらったところ、「泥・尾・敵・襲」など上学年の漢字も含めて11人の子どもたち全員がほぼ百%読めるようになっていた。しかも、まだ漢字を習い始めた段階の子どもたち全員が「一生懸命やれた」と答えている。上学年の漢字をルビ付き表記することは低学年でも十分可能であることを実証する実践となった。3年生でも試みた実践と併せてまとめてみた。一読いただければ幸いである。 低学年における「上学年の漢字ルビ付き表記」の可能性を探る |
| 2018年11月7日(水) 「オレオレ詐欺」の視点で読む |
5年の国語教材に「注文の多い料理店」(宮澤賢治作)がある。猟に来た二人の紳士が山猫の策略にまんまとひっかかっていく。その面白さを読みとって「解説書」を作ろう、という学習活動がよく行われている。そんな授業をいくつか見せてもらって思うことは、「この物語の本当の面白さに触れられていない。」ということである。 この物語を読んだ子どもたちは開口一番「何で気づかないの?この紳士らアホやなあ。」と言う。「立派な教養もある紳士」がたわいもなく騙されてしまうのはなぜか?それを解く鍵は冒頭に描かれている。そこがきちんと読めていれば「ああ、だからそう受け取ってしまうんだ」と、紳士の一つ一つの言動の奥にある心理が見えてくる。 注意を呼びかけているにも関わらず「オレオレ詐欺」に引っかかる人が今も大勢いる。なぜか?思わず信じこんでしまう状況が本人の側にあるからである。「紳士」も同じである。「注文の多い料理店」をオレオレ詐欺の視点で読むと数倍面白くなるのに……と授業を見るたび思う。 「注文の多い料理店の読み方」 |
| 2018年10月4日(木) 「授業の質」を外見で見てはいけない |
東書2年教材に「ビーバーの大工事」がある。授業研に関わることになり、教材解釈しながら宮教大学長林竹二氏の授業記録も読み返してみた。(「林竹二・授業の中の子どもたち」) 「人間について」というテーマで、ビーバーを題材に3年生で指導されたものである。授業の大半は林氏の話であり、その合間に、指名された子どもたちがぽつりぽつり発言するという静かな授業だ。だが、その授業を受けている子どもたちの表情がとても美しい。内面に深い集中が生まれていることが写真から見て取れる。子どもたちの感想文にも深い学びが綴られている。 たくさん発言していたら良い授業なのではない。本当に大切なのは、心の深いところで子どもの「主体が起きる」ことなのだと、改めて思う。 |
| 2018年9月17日(月) 「海のいのち」は優れた教材か? |
立松和平作「海のいのち」が6年生教材にある。優れた教材として評価が高い。だが、私はこの作品が好きになれない。「父を殺したあのクエを倒すのだ」という一念に全てをかけて生きる太一の姿が具体的に描かれ ることなく、「あらしさえもはね返す屈強な若者」とか「母の悲しみさえも背負おうとしていた」という叙述が唐突に出てくる。論理的な解釈はできても、情感が伴わない。叙述に無い部分を類推していくしかない。「それが『行間を読む』ということだ。優れた文学はそういうものだ。」と言われれば 自分の非力を恥じるしかないが、同じように省略的な表現で描かれた「川とノリオ」には すっと心が共鳴する。この違いは何なのか。この作品に対してぬぐいきれなかった私の違和感は、島根大学の冨安慎吾氏の論評を読んで氷解した。曰く、「『海のいのち』には「『ひとりの海』 という原作があり、それを絵本にするときに、大きく叙述を削り、さら に教科書版で挿絵も限定的になってしまったため、あちこちで「飛躍」が生じた」という指摘である。原作を読むと、例えば、「おとう、ここにおられたのですか」と言う太一の言葉も納得して読める。 授業者は教材解釈として、一度原作にも目を通してみられることをお勧めする。 「ひとりの海」はJUMPJBOOKSの「海鳴星」に掲載 |
| 2018年9月7日(金) 生活言語と学習言語 |
外国籍児童がたくさん就学する時代になった。だが、彼らにとって「言葉の壁」は高く厚い。本来、知的な遅れは無いのに学習不振で知的特別支援学級に入級しているケースも少なくない。 特別支援教育の専門家は言う。「『生活言語』は何とか身に付けられても、『学習言語』でつまづいてしまう。」と。確かに、授業の中で使われる言葉は、日常生活で耳にしないものも多い。抽象的な概念を表す熟語も3年生ぐらいから教材の中に頻出するようになる。「より多くの語彙を意味理解ととも獲得させることが重要」とその専門家は言う。これは、外国籍児童だけでなく、学習に困難さを感じている全ての子どもたちに当てはまることである。 今、実践を呼びかけている「漢字音読名人」は、語彙の宝庫である。例文を音読する中で、たくさんの未知の言葉に出会い、自然と語彙を増やしていくことができる。実践校から、「漢字音読名人に取り組んで子どもたちの語彙が増えた。」という報告もある。この実践の有効性を検証していただける先生が一人でも増えることを願っている。 |
| 2018年8月28日(火) 継続は力なり |
学校ぐるみで漢字の読み優先指導に取り組み、今年度も実践を継続しているG小学校。そのスキルアップタイムの様子を見せてもらった。チャイムが鳴るや否や、さっと友達同士で「漢字音読名人」の読み合いが始まる。友達3人に合格のサインをもらったら次に進むというルールなので、次々に相手を見つけてやっている。たまたま居合わせた私にまで、「ねえ、聞いて、聞いて!」と子どもたちが集まってくる。楽しくてしかたがないという表情だ。2年目になっても変わらず生き生きと取り組み続ける子どもたち。その姿に、この実践の有効性を確信する。 漢字が読める→文が読める→情報が掴める・語彙が広がるetc。何より、この取組によって、子ども同士の関係が開かれ、学級集団が温かなものになる。 |
| 2018年7月28日(土) 教師の仕事っていいなあ |
6月~7月の10時間、Y小の1・3・4年に水泳の指導をした。1年は「伏し浮き」、34年は「ドル平25m」全員達成を目標に指導した。「ずいぶん元気な先生がいるなあと思ったらあなたでしたか。」と笑われるほど一生懸命だった。 結果、1年生はやっと耳まで顔がつけられるようになった一人以外は全員伏し浮きで小プール端から端までいけるようになった。3・4年生は約半数が25m泳げるようになった。目標達成には至らなかったが、子どもたちが楽しく一生懸命練習してくれたことがうれしかった。最後の日、プールを出て行くとき、どの子もが「ありがとう!」と満面の笑顔で言ってくれた。「来年も教えにきてね!」と言ってくれる子もあった。「やっばり教師の仕事っていいなあ」と思えたこの夏のできごとだった。 |
| 2018年5月12日(土) ドル平を教えることに |
Y小校長から「妊婦の労働軽減の講師として、体育を教えてもらえないか」と頼まれた。曰く「前任校で先生からドル平を勧められ、やってみたら、子どもたちがとってもよく泳げるようになった。ちょうど水泳シーズンに入る頃になるので、ドル平を教えてやってほしい。」とのこと。 担任時代、ドル平で指導して、たくさんの子どもたちの笑顔を見てきた。また、そんな子どもたちの笑顔をみたいと思い、「老人」ではあるが引き受けることにした。 新学習指導要領には中学年でのドル平指導を許容する内容が書かれている。でも学校現場では、相も変わらずバタ足・面かぶりクロール一辺倒の指導で時間数だけ消化して事足れり、というところが多いのではないか。 ドル平のすばらしさを若い先生たちに伝えたい、そんな思いもあって、16年前に作った「ドル平指導の手引き」を整備しなおした。今回の仕事で、また新たな発見ができたら付け加えたいと思っている。 |
| 2018年4月29日(土) AI VS 教科書が 読めない子どもたち |
「ロボットは東大に入れるか」(東ロボプロジェクト)の新井紀子さん著「AI VS 教科書が読めない子どもたち」(東洋経済新報社)を現場の教師必読の書として推薦する。 AI技術の進展で、近未来、職業の半数はAIに代替されてしまうだろう。そのとき、人間の仕事はあるか。 AIの弱点は、計算機であり、「意味」を理解できないこと。しかし、今の中学生は、教科書の「意味」すら理解できない実態にある。このまま行けば、最悪のシナリオは、求人難でありながら、その仕事ができる人材が不足し、大量の失業者が出てしまうというもの。 今、学校教育が最重点にすべきことは、「きちんと教科書が読めるようにすること」。「一に読解、二に読解、三、四は遊びで、五に算数」と新井さんは言う。 3年前から提唱している「漢字が読める子に」と、ぴったり重なる。 |
| 2018年3月4日(日) 漢字指導のあり方を変えよう!⑥ |
◎「漢字が読めれば学びが変わる」 ~3年間の実践研究のまとめ~ 平成27年から取り組み始めた「漢字の読み優先指導」の検証実践。市教育研究所の紀要にその記録を掲載していただけることになり、まとめてみた。 紙数の関係で意は尽くせていないが、研究の概要と成果、そして今後の課題について、一定見えるものになったかと思う。 この実践が教育界に認められるものになるか、それとも消えてしまうか……。 もう1年、実践校が踏ん張ってくれれば、必ず確かな事実が生まれる。微力を尽くしたい。 |
| 2018年1月25日(木) 漢字指導のあり方を変えよう!⑤ |
◎「漢字音読名人」で仲間関係も深まった! 「漢字音読名人のおかげで、友達との関係が深まった」という感想をたくさんの子どもたちが寄せてくれている。友達同士で自由に聞きあい、チェックし合あって進むというスタイルが、子どもたちにとってはとても楽しい活動のようだ。「漢字音読名人をやっているおかげで、ペア学習もとてもスムーズにできるようになった」という担任の声もいただいている。 取り組んだ子どもたちのほぼ90%が「楽しくやれた」と答えその半数が「読書も好きになった」と答えてくれている。何より、漢字が苦手で学習もしんどいという子どもたちが「これならできる!」と生き生きと取り組んでくれているということがうれしい。 この取組がより多くの教室で試みられることを切に願う。 |
| 2017年9月18日(月) 漢字指導のあり方を変えよう!④ |
◎漢字の読み優先指導は中学校で一層有効! 私は小学校の教師だったので中学校の学習については詳しくない。 けれど、あの分厚い教科書の中に出てくる膨大な漢字の量を見れば、「漢字が読めないことには中学校の学習を理解することは全く不可能だ。」と誰だって思う。 今進めている「漢字音読名人」のような取組は、中学校でこそ真価を発揮するに違いない。そう考えて中学校版漢字音読テキスト「漢字音読検定1年~3年」も試作した。 さすがに中学校の漢字となると手強い。私自身も勉強し直しながらの作業だった。どなたか中学校の先生に試していただけたらうれしい。 |
| 2017年9月12日(火) 漢字指導のあり方を変えよう!③ |
◎上学年の漢字もルビ付きで表記する 「漢字の読み優先」と併せて提起していることは、「上学年の漢字もルビ付き表記で子どもたちに見せていこう。」ということ。 「漢字音読名人」は教育漢字の他常用漢字もルビ付き表記で使っている。これを難しいと感じる子は全く無く、むしろ未知の漢字を知る楽しさを感じている。 上学年の漢字もルビ付き表記で見せることは、新学習指導要領でも薦めている。江戸時代の寺子屋の教科書、「往来物」も総ルビ打ちで漢字の読み優先指導だった。 決して高度な学習ではない。むしろどの子も学びやすい方法なのだ。ぜひ、この方向での実践が広がってほしい。 |
| 2017年7月23日(日) 漢字指導のあり方を変えよう!② |
「◎読み書き同時進行ではなく、読み優先の指導を」 ということを提唱して一年余り。 賛同してくれた先生方の学級で「漢字音読名人」の取組をしていただいている。 うれしいことに、その全ての学級の子どもたちが、生き生きと練習し着実に力をつけている。とりわけ、漢字が苦手だという子どもたちが「これならできる!」と主体的になっていてくれる。 漢字の読み優先指導は、特別支援教育の視点から見ても有効だということを実証しつつある。 漢字の読みに特化した教材として、新たに漢字音訓カルタ等も試作し中。 試していただければありがたい。 学習に困っているすべての子どもたちが笑顔と自信を取り戻せる手立てになり得ると私は確信している。 |
| 2016年5月31日(火) 漢字指導のあり方を変えよう! |
◎6年生までに習う漢字はルビ付きで表記する。 ◎読み書き同時進行ではなく、読み優先の指導。 漢字習得はくり返し書いて覚えるしかない。その単調な「苦行」に耐える力も必要だ。 ほんとうにそうだろうか? 小学校1年生のとき、ひらがなの読み書きが全くできず、学校の教師もお手上げだった子がいた。家庭で教えるしかないと思ったその子のお母さんは、「漢字の表意性」に着目し、「一字に音と意味がある漢字を読むことから始めたら……」と考えた。一日漢字一字ずつ読み、その漢字を使った短文を子どもに言わせて、その文を読む、ということを続け、完全に読めるようになった後に「書き方」を教えた。 その結果、その子は6年生で教育漢字すべてを完璧に読み書きできるようになった。 この指導は、今の学校教育にそのまま応用できるはず。 そう確信した私は、その考えに立つ漢字指導資料を試作した。データをupしているので、ぜひ試していただきたい。 |
| 2016年4月5日(火) 虐待と学級崩壊の 根っこにあるもの |
「悪いことをしたら叱る。当たり前じゃないか。自分もそうやって育てられてきた。厳しくしつけることがなぜ虐待になるのか?」 「教室で勝手に立ち歩いたり私語をしたらみんなの迷惑。規律をきちんと守るよう指導するのは当然。なのに、ますます反抗的になってしまう。どうしたらいいの?」 自分たちが育てられたような指導・しつけが今の子に通用しない。なぜか?社会の劇的な変化の中で、厳然としてあった大人と子ども・親と子の縦の関係が解体してしまったからである。縦の関係では通用した権威的な指導も、フラットな関係では入らない。このズレに気づかず、旧来の指導から抜け出せないでいることが虐待や学級崩壊の根っこの問題としてある。 子どもも一人格として対等に向き合いつつ、社会の規範を身につけていくような子育て・指導法を確立していかねばならない。その重要な示唆がアドラー心理学にある、と私は思っている。 |
| 2016年3月17日(木) 「日本語の作文技術」 (本多勝一著)に学ぶ |
「長い修飾語ほど先に」・「句を先に」。 テンの二大原則 ①長い修飾語が二つ以上あるときその境界にテンをうつ ②語順が逆になったときにテンをうつ たったこれだけの原則を守って書くだけで劇的に読みやすい文章になる。 二十年以上前、この「日本語の作文技術」を読んで以来、この原則を心に置きながら文章を書くようにしている。 決して難しいことではない。子どもたちへの作文指導にも生かせる単純かつ重要な「作文技術」だと思う。 |
| 2016年1月29日(金) 「割合は小数倍の特別な表し方」 |
「学力向上支援員」として各学校を回っている。時節柄「割合」の授業を見ることが多い。どの教室でも子どもたちが困ってしまっている。「これは『もとにする量』?『比べられる量?』」と。黒板に書かれた線分図も、なかなか飲み込めない。こんな場面を見るたび思う。「『割合は小数倍の特別な表し方』とさえ言ってやれば、みんな分かるのに」と。 「500gの30%」は「500gの0.3倍」。だから「500×0.3」。この基本形をもとに□を使えばもとにする量も割合も簡単に立式できる。水道法式から学んだこの指導で、私の担任した子どもたちは、みんな割合の学習をクリアできた。 「倍」の意味から割合へと導くのが最も分かりやすい指導の道筋だと私は思う。 |
| 2016年1月21日(水) 「教育漢字を隠すことなく使用して作る、習ってない漢字にはルビを振る、ただそれだけのことです。」② |
私は今、機会あるごとに「ルビ付き漢字表記にしたテキストを作り、音読練習で試してみませんか」と、校長や教員に勧めている。ルビ付き漢字をくり返し読んでいるうちに、自然に上学年の漢字も読めるようになる。苦痛な漢字練習がうんと楽になる。まちがいなくそうなる。現場の実践で確かな成果が出れば、教科書会社も採用するだろう。文科省もこうした方向には柔軟な姿勢を示しているとのこと。 共鳴していただける先生は、ぜひ試していただきたい。 ということで提案していたら、3校から「おもしろい試みなのでやってみましょう。」と協力してもらえることになった。 子どもたちがどんな反応を示すか、楽しみである。 |
| 2015年12月27日(日) 「教育漢字を隠すことなく使用して作る、習ってない漢字にはルビを振る、ただそれだけのことです。」 |
ある方からこの指導法を聞いて、まさに「目からうろこ」だった。漢字表記であればすっと読めるものが、配当学年のしばりのため平仮名になってしまい、却って読みづらくなっている。市販の児童書にはルビ付きで漢字表記が普通であることを思えば、教科書の表記はいかにも不自然だ。著名な漢字学者の白川静氏も生前「そうあるべきだ」と言っておられたとのこと。 私は今、機会あるごとに「ルビ付き漢字表記にしたテキストを作り、音読練習で試してみませんか」と、校長や教員に勧めている。ルビ付き漢字をくり返し読んでいるうちに、自然に上学年の漢字も読めるようになる。苦痛な漢字練習がうんと楽になる。まちがいなくそうなる。現場の実践で確かな成果が出れば、教科書会社も採用するだろう。文科省もこうした方向には柔軟な姿勢を示しているとのこと。 共鳴していただける先生は、ぜひ試していただきたい。 |
| 2015年9月15日(火) 「希望の光ひとつ見つけた!」 |
とても勇気づけられる授業を見た。困難校と云われるS中学校三年の数学の授業。授業が始まり課題が出されてしばらくすると、生徒が席を立ち、あちこちで話し合いが始まる。結果を確かめ合う生徒、困っている生徒に寄り添って教えている生徒。ぼんやりしている生徒は一人もいない。やがて席に戻った生徒達は真剣な眼差しで教師の話に耳を傾け、次の課題に向かっていく。荒れて教室から飛び出す生徒がいて当たり前というこの学校で、50分間誰一人として集中を切らす生徒はいなかった。 後で子どもたちの授業の感想を読んで更に驚いた。2クラス58名全員が「こういう授業がいい、もっとしたい。」と異口同音に書いていた。 今、授業改善が叫ばれている。しかし、それは学力調査の数値を上げるためでしかない。真の授業改善とは、まさにこの数学の授業のように、すべての子どもたちの「学ぶ喜び・意欲」を保障するためのものでなければならない。そしてその見事な事実を私は観た。 |
| 2015年6月21日(日) 「梅雨時の水泳指導 に思う」 |
他県はどうか知らないが、我が県の大半の小学校は、6月中旬にプール開きをして、7月の学期末で水泳指導を終える。つまり、指導期間の大半は梅雨時なのだ。泳ぐのが苦手な子などすぐにプールサイドに上がってしまう。やっと夏らしい天気になったと思ったころはもう終わり。そして、夏休み明けの9月、酷暑の運動場で連日、運動会練習が続く。そんな不合理な年間計画が、疑うことなく、当然のこととして毎年繰り返されている。 私の勤務していた学校では、論議の末、酷暑の9月の運動会を陽春の5月末に移し、プール開きは7月初旬、夏休みを挟んで9月中旬まで、と大きく変えた。 子どもの泳力は飛躍的に伸びた。1学期の運動会も問題無くできた。そもそも、園年長児の実力を小学校の教師は知らなさすぎる。そして、梅雨時の6月は授業・学級づくりに専念して一年間のベースを作ろうということになった。 スクラップ&ビルドとはこういうことだと実感した一事例である。 |
| 2015年5月24日(日) 「因・縁・果」 |
曹洞宗の禅寺住職の話を拝聴した。 曰く「生老病死の苦に人は例外なく出会う。生きるとは、思い通りにならないところにどう向き合うかだ。」 「種まきを『因』とすれば、収穫が『果』。因と果をつなぐものが『縁』。縁は様々だ。人は『いいご縁』を喜び、『悪いご縁』を悔やむが、縁に「いい・悪い」など無い。色分けをしているのは自分自身なのだ。」 「池に『感謝』の石を投げれば感謝の波紋が広がり、『不足』の石を投げれば不足の波紋が広がる。」 すべて、自分の捉え方ででプラスにもマイナスにもなる。 話を聴きながら我が来し方を振り返ってみた。悔いたり恨んだり怒ったりの体験は数知れない。教師としての仕事の9割はマイナスの出来事だった。でも、今の自分を形づくっている中にそのマイナスの体験がある。60を過ぎた今、すべては「いい体験」であったと思えるようになった。 |
| 2015年5月20日(水) 「受け止めて、返す」 |
例えば、国語の授業で子どもが自分の読みを発表する。教師の期待する発言であれば、おおいに賞賛し、そうでない場合は、体よく聞き流す。こういう授業が続くと優等生だけが発言し、学習に自信の無い子は沈黙するようになる。どんな発言も「君はそんなふうに読んだんだね。」と受け止め、「どこからそう考えたのかな?」と返す。その子がうまく言えなければ「あの子の考え、誰か、『わかる』って人いない?」とまわりの子に返す。子どもたちは、自分の問題として考えだす。 例えば、子どもが問題行動を起こす。「なんてことしたんだ!」と叱責する。子どもは沈黙するか、泣くか、ふてくされるかだ。「どうしてこんなことになってしまったのか、聞かせてくれる?」とまずその子の思いを語らせる。「そうか、それで、こうなってしまったんだね。」と受け止める。そして「このあと、どうしようか?」と子どもに返す。子どもは自分の問題として考え始める。 「受け止めて、返す。」この一つのことを徹底するだけで、授業の質も生徒指導上の対応も劇的に変わる。私はそう確信している。 |
| 2015年4月30日(木) 「反対すれば非先生?」 |
古い同僚から声をかけられ4月からまた教育現場と関わる仕事を始めた。 しばらくぶりに見た学校現場は、ますます息苦しくなっていると思えた。数年前までは体力低下が大きな課題とされ、体力向上策がやかましく叫ばれていた。それがうそのように消え、今は全国学力調査のランキングに一喜一憂し、「学力向上」が至上命令となっている。加えて、いじめ防止対策や危機管理等々、次から次へと対応策が学校現場に求められていく。しかも、それらはどれも筋論から言えば正しいことだから、「できません。」などと反論することもできない。戦時中、戦争批判を口にしようものなら「非国民」とののしられたのとどこか似たような空気が今の学校現場を覆っている。 こんな時こそ、「教育学者」が声をあげるべきなのに、全く沈黙しているのはどういうことなのだろうか、と私の先輩が言っておられた。全く同感である。 |
| 2015年3月26日(木) 「記録の中から立ち上がる子どもたち」 |
雑多に保存してあるハードディスクの中から、3年生を担任したときの理科の授業記録が出てきた。「磁石」の学習の様子を学級通信に載せたものだ。「子どもっていろいろ考えるもんだなあ。こういう授業っていいなあ。」と、自分なりにうれしくて記録しておいたのだった。 もう25年も前のことなのに、記録を読んでいると、その時の教室の子どもたちの表情や声までがありありと蘇ってくる。 「良くも悪くも記録は残しておけよ」と先輩から言われ、それを愚直に実行してきた。残しておいてよかったと、今思う。 |
| 3月24日(火) 「説明できたら いいんですよ」 |
剪定の基本を庭師の先生に学んでいる。 先生曰く、「この枝を切るか、切らないか。いろんな考え方ができるわけで、方法は一つではない。要は『説明ができる』ことが大事なんです。自分は、こういうイメージに仕上げたいので切る、あるいは残すということがきちんと説明できるようにした上で鋏を使う。そうしておけば、成功・失敗の検証もきちんとできる。」と。 これもそのまま「授業」に置き換えて考えられる。 「授業展開の方法は一つではない。要は、『この授業でこんな子どもの姿を生み出したい。そのために、こんな指導案を考えた。』ということがきちんと説明できるようにした上で授業に臨むことだ。」 日々の授業もこんなふうに意図的に見ていきたい。 |
| 3月13日(金) 「音楽療法」 |
音楽療法の講師の話を聴いた。「歌を歌ったり、楽器を鳴らしたりしていると、NK細胞の数が増え、ガンの転移予防につながる。また、認知症を改善するホルモンの分泌を促進することがデータではっきり裏付けられる。」という。 その話を聴いて「確かに!」と私も思った。退職後の気晴らしに、夜のひとときアコギを弾いている。自己満足に過ぎないが、弾きながら歌っていると、体の中に高揚感のようなものが湧き上がってくる。たぶんそういうことなのだろう。 遙か昔、神戸の四郷小の公開研究会で心がふるえるほどの子どもたちの歌声を聴いた。四郷小の先生たちが合唱指導を始めたのは「すさんだ子どもたちの心を少しでも軽くしてやりたい。」という思いからだったという。それは、音楽療法の視点からも全く正しいことだったのだと今更ながら思う。 |
| 3月3日(火) 「わかる」言葉 |
町民健康講座で昭和大出浦照國氏の話を聴いた。2日間、計9時間、最後まで夢中で聴き入った。「メタボはガン以上に恐ろしい」ということがよく分かった。 それとは別に出浦先生の講演から強く学んだことがある。それは「わかる」ということ。 「スライドを使えば、その時は分かったような気になるが、会場を出たらほとんど忘れている。私はプリント資料だけで話す。その代わり皆さんが確実に分かるように話す。」と云われ、全くそのとおりであった。メタボの仕組みも専門用語も非常に具体的な「分かる」言葉で話された。帰ってプリントを見ても講義の中身がくっきりと見えてくる。 教師は、「分かる」言葉で教室の子どもたちに語っていかねばならない。 出浦先生の授業を受けた「生徒」の実感である。 |
| 2月28日(土) 全国学力テスト最下位 の滋賀 |
H26年度全国学力調査の結果、滋賀県は最下位だった。汚名挽回すべしと、県教委から「学力向上」に関する様々な指示が出され、その対応で学校現場が更に多忙化しているとのこと。 正答率トップ秋田の41.4と最下位滋賀36.0の差はそんなに深刻なものなのか?数字に幻惑されて授業の質が更にいびつなものになっていくことを危惧する。 昭和30年代、島小(斎藤喜博校長)の子どもたちの学力は六大都市の平均を超え、しかも学年が上がるほどその伸びは顕著であったという。映画「芽をふく子ども」に記録されている「島小の授業」。ぜひもう一度観てほしい。現場の教師が何をこそ追求すべきかがきっと見えてくる。 |
| 2月25日(水) 「面白い」とは どういうことか |
今朝の朝日新聞リレーおぴにおん。生物学者の大沢文夫先生の言葉 「先生が口を出してはいけないんです。ついついケチもつけたくなるけれど、ぐっと我慢する。自分で見つけた問題を自分でやってこそ喜びも深くなる。たとえ小さくてもね。面白いというのはどういうことか、自分で知る必要があります。今の先生たちは口を出しすぎるし、でしゃばりすぎでは。……教えてもらったものでは自分のものにならない。」 算数の授業で、答を教えようとすると、「ああ、まだ言わんといて!」と言って自分で考えたがる子どもたちの姿と重ねて読んだ。 「こどもは、『観客』より『プレーヤー』になりたいのだ」と、昔、先輩から教えられた言葉も脳裏に浮かぶ。 |
| 2月23日(月) 物語文の授業って? |
「モチモチの木」の授業研究会に招かれた。 自分の記録は残してあるがずいぶん古い。「今、どんな実践が行われているのだろう」とネットにupされている記録をランダムに読んでみた。 pisa型学力が強く叫ばれ、「分析」「比較」「表現」等を重点とする実践が並んでいる。とりわけ「分析・評論」的に読ませようとする記録が多いように思われた。物語文の授業がともすれば叙述から離れた勝手な想像のやりとりや、字面だけを追う授業に終始していることがその背景にあるのだろう。 だが、素朴に思う。「こういう授業は子どもにとって楽しいだろうか?」と。 本来物語文は「読み味わう」ものなのに、小さな学者のように冷徹に文章を切り刻んでいくような読ませ方に私は同意できない。 「叙述に即してイメージ豊かに読み描く」という読みの基本に立つ実践がもっともっと出てくるべきだと思う。 |
| 2月15日(日) 庭師の目 |
荒れた古寺の庭園整備にボランティアとして参加している。 指導して下さる庭師がこんなことを言われた。 「この寺に入って来られた方は、どこに目を留めるだろうか。そこに何があるとほっとした気持ちになるだろうか。物によって、心がスッと奥に入って行けたり、跳ね返されてしまったりする。庭をつくるとき、私はいつもそのことを考えている」 教材研究も同じだと思う。「この教材をどう教えようか」という教師の視点だけでなく、「子どもは、どんなふうにこの教材を見るだろう。どんな学びの道筋だとすっと教材の中に分け入っていけるだろう」と子どものまなざしで教材を捉えていくこと、それが授業づくりの要になる。 |
| 2月13日(金) ハナノキはなぜ枯れた? |
家から車で15分ほど行ったところに国の天然記念物「ハナノキ」がある。自生するハナノキとしては日本最西端にあり、巨木としても知られていたが、残念なことに主幹部が腐朽して数年前倒壊してしまった。 なぜハナノキは枯れたのか? 「大切な木を守らなくては」と考えた地域の人たちが、木の回りを石垣で囲い、むき出しになっている根を丁寧に土で覆った。 木の根は、本来表土すれすれのところに伸びる。呼吸するためだ。その根を密封してしまったものだから、木は窒息状態になり、枯れてしまったのだ。 「地獄への道は善意によって舗装される」 その言葉のとおりである。 教育・子育ての場でもハナノキと同じことが起きている。 |
| 2月8日(日) 知的好奇心 |
町の古文書学習会に入会し、古文書解読の勉強を始めて1年になる。 最初はうねうねとした墨の筋にしか見えなかった古文書だが、ポツポツと文字が浮かんでくるようになり、定番の言い回しが読めるようになり、近頃はあらましが読み下せるようになってきた。「そんなの何がおもしろいの?」と妻は笑うが、できなかったことができるようになっていく、見えなかったものが見えるようになっていくというのは理屈ぬきに楽しい。 学校で学ぶ子どもも同じだろう。「荒れて授業が成立しないから」と言って、毎日プリント学習にしたら更にひどく荒れてしまったという話を聞いた。当然である。 水道方式の生みの親、遠山啓は言う。「強烈な好奇心が人類進化の原動力であり、好奇心・探究心が全面的に発動するような条件をつくってやれば、子どもはやるなといっても自発的に行動する」と。 |
| 2月4日(水) 児童虐待の現場に立ち会って |
退職後2年間、児童虐待に関わる家庭児童相談員の仕事をさせていただいた。 児相職員に同行して初めて訪問した家の玄関先で「いつまで来るんじゃ!」と怒鳴られた。足の踏み場も無い「ゴミ屋敷」の家にも入った。ケースによっては土日・深夜に及ぶこともあり、現職時代と変わらぬハードな日々だった。 精一杯「支援」を続けてもほとんど何も変わらない現実にしばしば心折れそうにもなった。でも、その中で新たな学びも多々あった。教員時代の記録がおおよそ整理できたので、この後は、家庭児童相談員としての2年間で学んだことを整理してみたいと思っている。 |
| 2月2日(月) 「イスラム国」と「困った子」 |
今朝の朝日天声人語欄にこう書かれていた。 ─イランの映画監督マフマルバフ氏がかつて、大意こう述べていたのを思い出す。「(アフガンなどの)タリバーンは遠くから見れば危険なイスラム原理主義だが、近くで個々を見れば飢えた孤児である」─ そこを読んではっとした。「『困った子』は実は『困っている子』という見方と全く同じだ。」と。 教師の指示を無視し、好き勝手なことをして友達に迷惑をかける子。そういう困った子をびしっと厳しく指導すれば収まるか?否、反発を倍加させるだけである。テロに対する力による制裁も同じ。報復の空爆など、一層残虐なテロ行為を引き出すだけのこと。どんなに困難でも、冷静に対話で道を開いていくしかない。 生徒指導の原則は国レベルの問題にもそのまま当てはまる。 |
| 1月31日(金) 特別支援教育と授業研究 |
教師生活最後の10年間は特別支援教育との関わりが深かった。 「『困った子』は、実は『困っている子』なのだ」という見方はまさに“目から鱗”であり、職場の仲間でいろんな取り組みをやった。当時としては先進的な取り組みとして評価もしていただいた。 特総研の藤井先生は「特別支援教育の実践とは、その教室で行われている授業の質の追求に他ならない。」と言われる。まさにその言葉どおり、若き日、「教室のボトム(底)にいる子の視点から」を合い言葉にあれこれやっていたことが、50代での特別支援教育の実践にぴったり重なっていった。 私の特別支援教育に関する実践の土台は30年前の豊小で形づくられていたのだった。 |
| 1月28日(水) 離見の見 |
ある学校の研究会で、「自分の授業をVTRに撮って見たことがありますか?」と尋ねてみたら一人もいなかった。 こんなにデジタル機器が手軽に扱える時代になっているのに、なぜ? 忙しくてそんな暇が無い、などといいわけするが、本音は「自分の姿を見たくない」からだろう。 私自身、初めて自分の授業をテープにとって記録を起こしてみたとき、5分と聞いていられなかった。 でも、自分で自分の姿を客観的に見つめるということを抜きにして教師としての成長などあり得ない。 世阿弥の言葉に「離見の見」というのがある。若き日に教えられメモしておいたものがあったので、「私の学習帳」にupしておいた。 |
| 1月26日(月) 物語文の教材解釈=文章の映像化 |
保存データの中から、若林達也先生の「実践:授業入門」から抜き書きした「教材解釈の手法」が出てきた。 教材解釈の方法について述べた著作はいくつもあるが、具体的かつ明確という点においてこれ以上のものを私は知らない。自分が教材解釈を進める際、常によりどころとしてきたものである。「私の学習帳」にupしたので一読していただきたい。 物語文の教材解釈をひと言で言えば、「文章を映像化する作業」と言えるのではないか。今、私はそんなふうに思っている。 |
| 1月16日(金) 芽をふく子ども |
劣化するVTRテープをDVDにコピーする作業を再開し、年の初めにまず「芽をふく子ども」を選んだ。 群馬県の島小学校の一年を記録した映画だ。斎藤喜博校長と島小教師集団の映像による実践記録でもある。 授業の中の子どもたち、そして教師の表情のなんと美しいこと。授業に深く集中し、一点を見つめて考え込む子、教師や友達の言葉に耳を澄まして聞き入る子、教室の中の子どもたち一人ひとりが響き合い、一体となって追求している姿は、今見ても私の心を奥底からゆさぶる。 「こんな教室をつくりたい。」とあこがれ、私はやってきた。結果は遠く及ばないままだったが……。 今歩み始めたばかりの若い先生方にはぜひ観てもらいたい。子どもたちの未来をひらくために。そして教師としての我が身のありようを考えるために。 |
| 1月7日(水) かけだしのころ |
自分の初任の頃の記録もここに収めておきたくて古い記録を引っ張り出してきた。 山の学校で過ごしたなつかしい日々が記録の中から立ち上がってくる。 教師として打ち込めるものを見つけようとあれこれ模索していた。今読み返すと恥ずかしくなるようなこともいっぱいやっていた。でも、子どもと一緒に創っていくという基本には立てていたのかなとも思う。 ほんとにいい時代に教師になれたと思う。もし今、自分が教師になったら、たぶん潰れてしまうだろう。そう思えるほど、今の学校現場は厳しい。 でも、そんな中でも若い先生たちが生き生きと仕事をしている姿がある。その若い力をまっすぐに伸ばしていってほしいと思う。 |
| 2015(H26) 1月5日 年の初めに |
また新しい一年が始まった。 退職後、有り余る時間をもてあますのではないかと不安だったが、「24時間すべて我が裁量」という生活の中で逆に時間を意識的に使うようになり、思いの外いろんなことにチャレンジできた。 今年もあれこれ目標をたくさん立ててみた。 その中の一つが、まだ整理しきれていない記録をこのHPにまとめること。他者から見れば取るに足りないものばかりだが、自分の生きてきた証を形にしておきたいと思う私の終活作業でもある。 |
| 12月26日(金) I am OK |
N幼稚園の保護者の皆さんに幼児期の子育てについて話をさせていただいた。 「I am OK」は私自身の座右の銘でもある |
| 11月24日(月) 初任の子らの同窓会 |
山の分校で私は教師のスタートを切った。 そのとき担任した子が同窓会に招待してくれた。 今年50歳になったという。 みんな、すっかりいいおっさんおばさんになっているが小学校の頃の面影がどこかに残っている。 まだ教師として何の力もない私のような者にも保護者の目は温かくのどかな時代だった。 あの山の学校での楽しい数年が私の教師人生の礎石となっている。 |
| 10月25日(土) VTR紙芝居「つるのおんがえし」 |
特別支援学級(当時は『障害児学級』)を担任していたときの記録を段ボール箱の中から取り出していたら、VTR紙芝居「つるのおんがえし」が出てきた。不登校寸前だったとは思えないHちゃんの張りのある音読の声。心が開かれるとこんなにも生き生きとした姿を見せてくれるのだということを私はHちゃんから学んだのだった。 |
| 9月30日(火) 話すということ |
今、国語科では、「話すこと」の指導が重点事項の一つになっている。指導の手立てとして、どの学校でも「声のものさし」が使われている。悪いとは言わないが、「声」の本質に根ざさない実践は「形」だけになる。竹内敏晴氏が「話すということ」について、最も根源的なことを述べられているので、「私の学習帳」にそのメモをupした。 |
| 9月2日(火) 学級崩壊はなぜ起きる? |
ホワイトボードミーティングで有名なちょんせいこさんを招いて研修会をもったことがあった。児童虐待のケース会議の進め方を学ぶことが目的だったが、その中で「学級崩壊はなぜ起きる」ということについて話されたことが心に残りメモしておいた。「私の学習帳」にそのメモをUpした。 |
| 8月21日(木) N先生の個展 |
初任者指導の先生として来ていただいていたN先生から個展の案内をいただいた。若い頃棟方志功の版画に魅せられ、教職のかたわら独学で版画制作を続けてきたとのこと。 魅力的な作品が並んでいる中、年賀状用に彫ったという幼児のあどけない笑顔の作品が、とりわけ私には好ましく見えた。困難校でしんどい子どもたちと向き合ってこられたN先生の温かな眼差しがそこに凝縮されているように思えた。 |
| 8月7日(木) キーカラカラ キークルクル |
「たぬきの糸車」という教材でおかみさんが回す糸車の音をこう表現している。 子どもたちはリズムがいいので楽しげに音読してくれる。糸車のしくみをよく知らない私は、それで良しとして授業していた。 ふとyoutubeで糸車を検索したら糸車で糸を紡ぐ動画が出ていた。なるほど「キーカラカラ キークルクル」になっている。子だぬきが「くりくりした目」で夢中になるのも当然といえるほどのおもしろさがある。 教材について具体的なイメージをもっていることで子どもの読みに対応できる幅も広がる……教師をやめても、そんなことが頭に浮かんでくる。 |