| 授 業 記 録 |
| 5年 |
「公害」の学習
1987年豊郷小5年 |
日本の工業がかかえる様々な問題の中で、公害は直接人間の生命にかかわる重要な問題である。「水俣病」「イタイイタイ病」「四日市ぜんそく」「光化学スモッグ」「酸性雨」…… こうした公害がなぜ起こるのか、公害問題をどう解決していけばいいのか、ということについて子どもたちに考えさせようと思った。そのためには一つの公害問題に絞って、その発生からの足取りをたどってみることが一番良いのではないかと考え、公害問題の原点となった「水俣病」を取り上げ、学習していくことにしたのだった。 |
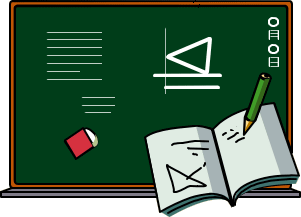 |
| 6年 |
「自然とわたしたちのくらし」①
1987年豊郷小5年 |
富山和子 著 「川は生きている」(講談社)
「水と緑と土と」(中公新書)を教材として授業化したもの。中世と明治以降の治水工事の比較から「自然との共生」を考えさせた。
|
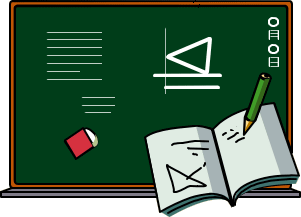 |
| 6年 |
「自然とわたしたちのくらし」②
1987年豊郷小5年
|
ナイル川に建設されたアスワンハイダムの功罪から「自然との共生」の重要さを考えさせた。 |
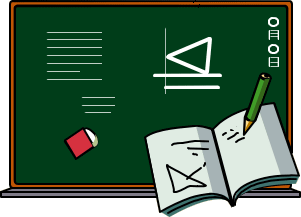 |
| |
解放令以後の最下層の民衆の暮らし
1988年豊郷小6年 |
「解放令」によって最下層の人々は、制度上は他の農工商の人々と対等にはなったけれ
ど、実生活では逆に江戸時代以上のきびしい状況に置かれるようになったことを理解させるねらいで授業したもの。
|
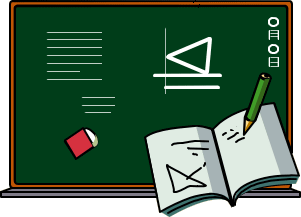 |
| 6年 |
野麦峠を越えた人々
1988年豊郷小5年 |
明治に入って急速に近代工業が発展していった背景に大量の貧しい小作農民層が、労働の供給源として存在していたことを理解させるねらいで授業したもの。 |
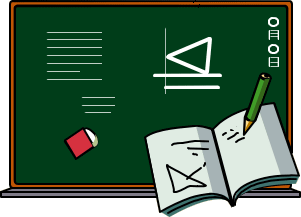 |
| 3年 |
地域に伝わる伝承行事
1999年八日市西小3年 |
「昔のくらし」の単元で、地域に今も伝わる伝承行事を子どもたちが調べたもの。 |
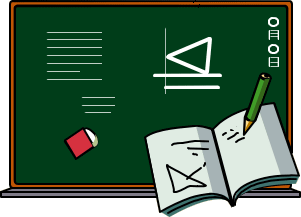 |
